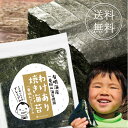2020年2月3日は節分。
豆まきをしたり、近年は恵方巻を食べる習慣も定着しつつあり、私たちにとってなじみのある行事ですね。
今回は節分の豆まきの由来や豆まきのやり方・恵方巻やいわしなどの節分の伝統・過ごし方について解説します。
節分 2020年の恵方の方角
2020年(令和2年)の恵方は西南西。
細かく言うと、西南西のやや西(右)です。
庚の方角です。
2020年の節分は2月3日です。
ただ、これは固定されている日付ではなく、2021年から2100年までは2月2日が節分となります。
恵方とは?
恵方とは、歳徳神(としとくじん)という神様のいる方角のこと。
歳徳神は「年神様」とも呼ばれる、その年の幸福をつかさどる神様です。
年神様のいる方角は毎年異なり、
恵方は「その年の縁起の良い方角」です。
恵方巻づくりに。
送料無料のネギトロ、楽天の人気商品はこちらです。
送料無料 王様のネギトロ 200g ネギトロ丼で約2人前 まぐろたたき
節分に豆まきをする理由・豆まきの由来
節分とは
節分とは「季節を分ける」という意味です。
もともとは「二十四節気」の「立春・立夏・立秋・立冬」の前日のことを「節分」といいました。
旧暦では新年は春から始まるため、特に立春の前日の節分は、大晦日に相当する日でした。
そのため立春の前日の節分は、1年の節目として特別な日となり
室町時代ころからは、節分といえば春の節分をさすようになりました。
節分と鬼の関係
古代では、天変地異などの災害や病気、飢饉など、人間の力ではどうすることもできない恐ろしい出来事は、
鬼や魔物など邪悪な存在、邪気によるものと考えられていました。
古来の日本では、物事を「陽」というプラスのエネルギーと「陰」というマイナスのエネルギーの作用で成り立っているとする陰陽道の考え方が広まっていました。
大晦日にあたる節分の夜は、1年の中で最も陰と陽のバランスが乱れる日と考えられていました。
このような日には、普段姿を隠している鬼や魔物が出現しやすく、
そのため、節分の夜には鬼を追い払い、福を呼びこもうとする風習が広まるようになりました。
節分と豆まきの由来
節分の豆まきの由来は、古代中国にさかのぼります。
古代の中国では、大晦日(おおみそか)に「追儺(ついな)」というお祓いの行事が行われていました。
追儺、鬼やらいともいわれるこの行事は、魔除けの力がある桃の木で作った弓矢を射て、鬼を追い払うというものでした。
その習慣が日本に伝わり、706年に始まりました。
平安時代には、追儺は宮中で役人が、桃の弓と葦の矢で内裏(だいり=天皇の住まい)の中から魔物を追い払う年中行事として行われていました。
鬼を示す役割をした役人と、鬼を追い払う役目の人々が行事を執り行っていました。
次第に、鬼を追い払うために豆をまく風習が広まり、室町時代ころに庶民の間にも豆まきが定着するようになりました。
一方、宮中での鬼やらいは鎌倉時代ころから行われなくなっていきました。
折り紙での立体的な鬼の作り方はこちらの記事にまとめています。

節分に「大豆」をまく理由は?
大豆は五穀のひとつ。
穀物の霊が宿ると考えられており、神事に用いられてきました。
大豆は米よりも粒が大きく、ぶつけた時の音も大きいので、邪気を祓うのに適していること、
「まめ」という言葉が
「魔の目を射る」「魔を滅する」(魔滅=まめ)に通じる
都を荒らす鬼に豆をぶつけて追い払ったという伝説がある
などの理由から豆が用いられるようになりました。
豆まきに用いられる豆は炒った大豆を使用することが多いです。
その理由は、生の豆をまいて拾い忘れたものから芽が出てしまうと縁起が悪いとされているからです。
また、「炒る」は「射る」にも通じており、「豆を炒る」が「魔の目を射る」という意味につながるからです。
ただ、北海道や東北、九州などには落花生を使用する地域もあります。
乾燥した落花生は豆を炒る手間がなく、落ちた豆も殻をむいて簡単に食べることができて手軽なため、北海道では節分の時期は落花生が店頭には並びます。
節分の豆まきのやり方
豆まきの仕方も地域やご家庭によって様々ですが、典型的なご家庭での豆まきのやり方をご紹介します。
豆を準備する
すでに炒ってある大豆を購入するか、生の大豆を炒って豆まき用の豆を準備します。
炒った豆は、豆まきまで枡に入れておきます。
神棚があればお供えしておきましょう。
豆をまくのは節分の夜
鬼が住むとされる「鬼門」の方角は丑寅、北東です。
時刻としては深夜の2時~4時ぐらいですので、鬼は真夜中に北東からやってきます。
そのため、豆まきは夜に行います。
家族全員が揃ってから行いましょう。
豆をまく人
豆まきをするのは一家の家長や、年男、年女、あるいは厄年にあたる人が行います。
もちろん家族全員で行っても構いません。
「鬼は外!福は内!」と掛け声をかけながら豆を撒く
家の奥の部屋から玄関の方へ順番に鬼を追い出すように、すべての部屋で豆をまきましょう。
家の中に豆をまくときは「福は内」と声をかけます。家の中に巻いた豆は「福豆」といって縁起ものなので拾いましょう。
家の外に豆をまくときは「鬼は外」と声を掛けます。
窓から外へ投げたり、玄関から外へまきます。
外に巻いた豆は拾う風習もあれば、そのままにしておく地域・ご家庭のやり方があります。
鬼神を祭神としている神社・寺社や、苗字に「鬼」が含まれる姓の多い地域などでは「鬼も内」という掛け声をかけるところもあります。
拾った豆を入れる豆入れの折り紙での作り方はこちらの記事にまとめています。

豆を食べる
豆をまき終えたら、豆を食べましょう。
1年の厄除けを願って、豆を食べます。
食べる数は
満年齢の個数だけ、または数え年として1つ多く食べる、数え年と新年の分を加えて2つ多く食べる、など
考え方は地方によって異なります。
数が多い場合には、福茶を飲む方法もあります。
「恵方巻き」の由来
近年定着してきた感のある、節分の太巻き「恵方巻」。
恵方巻の由来は、大正時代に大阪から広まった風習だといわれています。
節分の時期に、海苔巻きを作ります。
そしてその年の「恵方」と呼ばれる、「その年の最も縁起が良い方角」を向いて
願い事をしながら食べます。
最後まで丸かじりすると、願い事が叶う、健康でいられる、商売が繁盛するなどの幸運をもたらすとされています。
全国に広まるようになったのは比較的歴史が浅く、
1989年(昭和64)にコンビニエンスチェーンが広島県で太巻きを売りだしてから。
全国販売されるようになったのは1998年(平成10年)から。
近年は恵方巻の人気と共に食品廃棄問題もクローズアップされており、予約制にしているコンビニチェーンなどもあります。
恵方巻には、七福神にあやかって7種類の具を入れた太巻きを食べるとさらに縁起が良いとされています。
包丁などの刃物で切ると「縁が切れる」「福が逃げる」と縁起が悪いので、切らずにそのまま食べます。
食べている途中で喋ってもいけません。
節分の恵方巻きの食べ方
巻き寿司をひとり1本準備する。
包丁などで切らずに1本丸ごと食べます。
その年の恵方を向く。
恵方とは、その年の福を授ける年神様(歳徳神)がいる方角で、その年最も良い方角とされています。
食べ終わるまでよそ見をしてはいけません。
願いごとをしながら、しゃべらずに最後まで食べる。
口をきくと運が逃げてしまうため、食べ終わるまで話をしてはいけません。
楽天で大人気、送料無料の海苔はこちら
節分といわし・ヒイラギの関係
節分の風習として、いわしを飾る文化もあります。
鬼は、鰯(いわし)の臭いや焼く煙と、柊(ひいらぎ)のトゲが苦手といわれています。
そこで、鰯の頭を焼いたものを柊の枝に刺し、玄関の門口やしめ縄につけることで魔除けとする「焼嗅(やいかがし)」という風習があります。
「鰯柊」「柊鰯」「柊刺し」などの呼び方もあります。
外ではなく自宅に飾ったり、節分に鰯を食べる文化の残る地域もあります。
まとめ
節分の由来、豆まきの仕方や恵方巻、いわし・ヒイラギについてご紹介しました。
1年の厄除けを願う豆まき。
幸福の絶えない、明るい家庭で1年を過ごしていきたいですね。